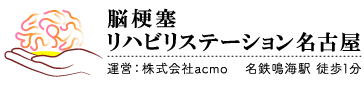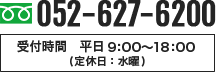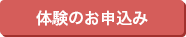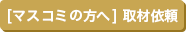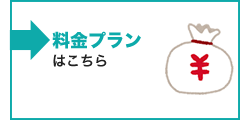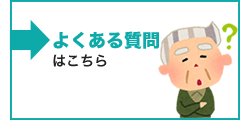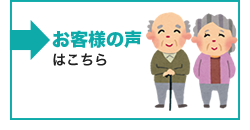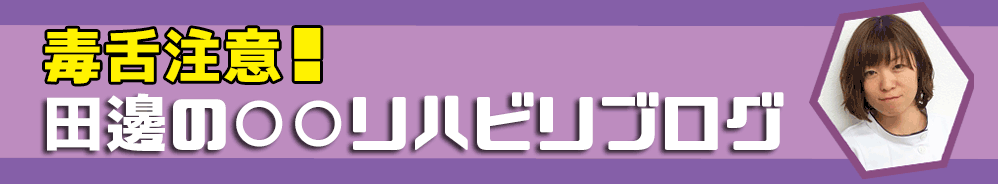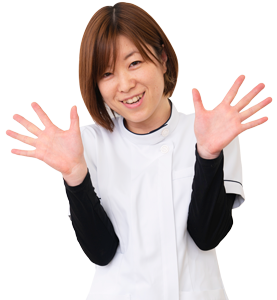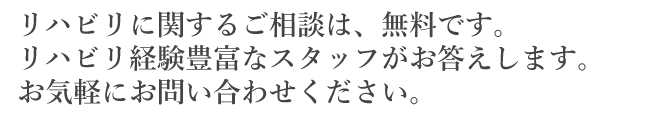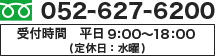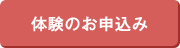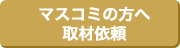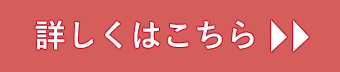お知らせ | 名古屋を中心に脳梗塞のリハビリをサポート!
- 脳梗塞リハビリステーション名古屋
- リハビリの現場から 脳リハ名古屋ブログ
- 片麻痺のリハビリ初期にやること
片麻痺のリハビリ初期にやること
2025.06.13
リハビリの現場の様子を
ブログで紹介しています。
リハビリのことが
少しでも伝わると嬉しいです。

目次
—動かすより前に、大切な“はじめの一歩”—
突然「片麻痺です」と言われたとき、頭が真っ白になった方も多いと思います。
「これからどうなるの?」「ちゃんと歩けるようになるのかな…」
そんな不安な気持ちに、少しでも光が差すように。
今回は、リハビリの“初期”に取り組む大事なことについて、わかりやすく、でもちょっぴり専門的にもお話しします。
1. 【自己認知】自分の体の“今”を知ること
リハビリの初期で一番大事なことは、「自分の今の状態を知ること」です。これは“自己認知(self-recognition)”と呼ばれるリハビリの大切なプロセス。
「どこが動くのか?」「動かそうとしてどんな感覚があるのか?」
そういった情報を、脳と体がもう一度つながっていくように確認していきます。
たとえば「右手を上げよう」として、実際に上がらなくても、“上げようとした”意識がまず大切。
これは“随意運動”と言われ、自分の意志で体を動かす回路の再起動のようなものです。
2. 【座位保持】座れることは、生活の再スタート
ベッドから起きて、“座れる”こと。これはリハビリ初期でとても大切な目標です。専門用語では“座位保持”といいます。
座るには重心のコントロール(バランス)、体幹の安定性、両足の支持感覚など、たくさんの要素が関わります。
このとき私たちは、抗重力筋と呼ばれる、体を支える筋肉たちを使っています。
3. 【感覚入力】動かす前に、“感じる”ことから
リハビリというと“動かす”ことに注目しがちですが、実はその前に大切なのが“感覚入力(sensory input)”です。
これらはすべて、「脳が体を感じているか?」の確認です。特に脳卒中後は、深部感覚(しんぶかんかく)という“関節の位置や動きを感じる感覚”が鈍くなることがあります。
4. 【環境調整】身体を動かしやすくする“土台”を整える
リハビリ初期では、「どう動くか?」よりも「どういう状態なら動きやすいか?」を整えることがポイントです。
これは環境調整(positioningやsetup)と呼ばれます。
環境は、「できる・できない」を左右するほど大きな要因。
無理に動こうとする前に、「自分が一番ラクに感じる姿勢」を見つけていきましょう。
5. 【成功体験】“できた!”という感覚を脳に刻む
最後に、これが一番大切かもしれません。それは、“成功体験”です。
たとえ小さなことでも、それらはすべて、脳にとっての“再学習のきっかけ”になります。
神経の世界では、“使った神経が強くなる”という性質(可塑性=プラスティシティ)があります。
さいごに
片麻痺のリハビリは、ゴールが「治す」だけではありません。
“今ある体と、どう仲良くなっていくか”を探す旅のようなもの。
今日の1ミリの変化を、明日の自分にプレゼントするような感覚で——
あなたのペースで、歩き始めてください。
わたしたちは、その歩みに寄り添っていきます。

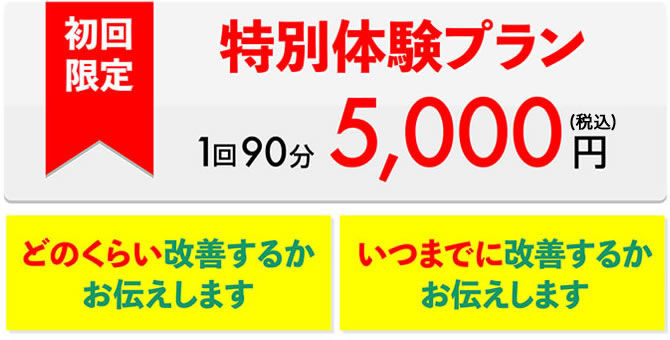


2026年 1月 01日
謹賀新年~新体制~
年が明けましたね。 みなさま、どうお過ごしかしら。 餅、詰まらせてな...
続きを読む
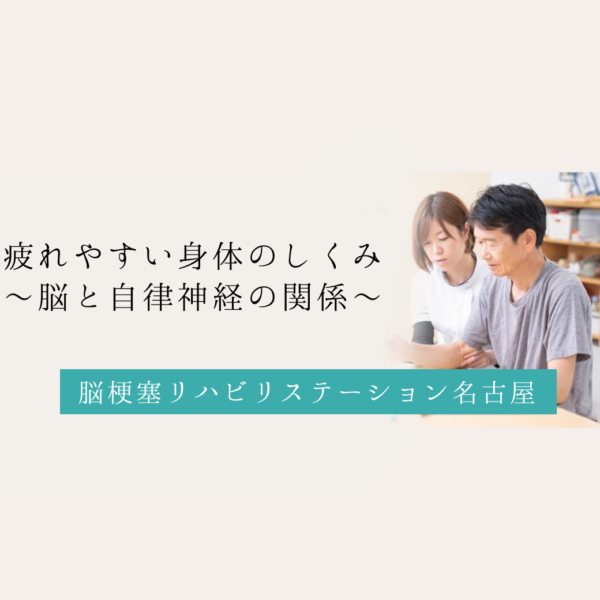
2025年 12月 12日
疲れやすい身体のしくみ 〜脳と自律神経の関係〜
疲れやすい身体のしくみ 〜脳と自律神経の関係〜 「リハビリを頑張っているのに、すぐ疲れてしまう」「...
続きを読む

2025年 10月 06日
上肢と下肢、回復しやすいのはどっち?
上肢と下肢、回復しやすいのはどっち? 脳卒中後のリハビリで「手と足、どちらが回復しやすいの?」...
続きを読む